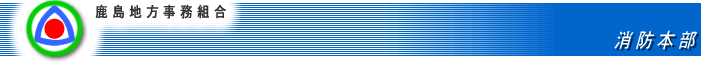 |
|
| |
|
危険物製造所等手続要領 |
 |
|
|
| |
|
著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に対する消火設備の指導基準
|
| |
| |
| この基準は、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第33条第1項第1号に定める |
| 製造所及び一般取扱所のうち、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分 |
| において危険物を取り扱う設備を有するもの(以下「6m以上の危険物取扱設備」という。)、並び |
| に同条第2項第1号に定める、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等(以下「煙が充満する |
| おそれのある場所」という。)に対する消火設備の設置に係る事項について定めるものとする。 |
| |
| 1 6m以上の危険物取扱設備に対する消火設備について
|
| (1) 塔、槽類(20号タンクを除く。以下同じ。)については、適応する固定消火設備を設置 |
| することが原則であるが、これと同等の効果のある代替設備(次の(2)に掲げる設備等)を |
| 設ける場合は、危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)第23条を適用するこ |
| とができる。 |
| (2) 冷却散水設備、不活性ガス送入設備及び水噴霧消火設備を代替設備とする場合は、次の |
| 事項によらなければならない。 |
| ア 冷却散水設備 |
| ① 塔、槽類の6m以上の部分すべての表面を散水ヘッドから放射する散水によって冷却 |
| するように設けること。 |
| ② 散水量は、塔、槽類の表面積1㎡につき5L/min(断熱施工されている場合は2.5L/ |
| minとする。)とし、30分以上連続して散水できる水量を確保すること。 |
| ③ 塔、槽類が複数ある場合は、表面積が最大の塔又は槽類の水量及びポンプ能力を有す |
| すること。 |
| イ 不活性ガス送入設備 |
| ① 塔、槽類の全内容量を充満するのに必要な不活性ガス量を確保するとともに、有効に |
| 5分以内で送入できる設備であること。 |
| ② 危険物を攪拌しない設備であること。 |
| ③ 塔、槽類が複数ある場合は、全内容積が最大の塔又は槽類の不活性ガス量を有するこ |
| と。 |
| ウ 水噴霧消火設備 |
| ① 塔、槽類において、予想される最大液面高さまでの範囲に設けられる200A(外形2 |
| 16.3mm)以上のノズル及びマンホール等の部分には、放射する水噴霧によって有効 |
| に消火することができるように噴霧ヘッドを設けること。 |
| ② 塔、槽類が複数ある場合は、放射量が最大の塔又は槽類の水量及びポンプ能力を有す |
| ること。 |
| ③ その他規則第32条の5によること。 |
| エ その他 |
| ① 冷却散水設備と不活性ガス送入設備は併せて設置すること。 |
| ② 塔、槽類の周囲に屋外泡消火設備を設置する場合は、塔、槽類の6m未満の部分につ |
| いて、冷却散水設備及び水噴霧消火設備を設けないことができる。 |
| ③ 塔、槽類以外の設備については、適応する固定消火設備を設置すること。 |
| |
| 2 6m以上の危険物取扱設備が存在することで著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に該当す |
| ることとなる場合は、6m以上の危険物取扱設備に対して固定消火設備を設置することにより政 |
| 令第23条を適用することができる。 |
| |
| 3 煙が充満するおそれのある場所とは、建築物又は工作物等(以下「建築物等」という。)の区分 |
| や、無窓階等で決定されるものでなく、現実に火災のとき煙が充満するおそれのある場所である |
| かを判断し、次のいずれかの場合は、該当しないものとして政令第23条を適用することができ |
| る。 |
| (1) 建築物等の1階の場合は、三方向の壁体に幅及び高さがそれぞれ0.75m以上及び1.2 |
| m以上の出入口があり、また出入口以外の開口部にあっては床面から開口部の下端までの高 |
| さが1.2m以内にある開口部の面積の合計が床面積の30分の1を超えるもの。 |
| |
| (2) 建築物等の2階以上の階の場合は、壁面のうち1の長辺を含む2面以上が外気に接する常 |
| 時開放された開口部が存ずる場所、長辺の一辺が外気に接する常時開放された開口部があ |
| り、かつ、他の一辺の壁体の面積の2分の1以上が外気に接する常時開放された開口部が存 |
| ずる場所で、火災の際煙が有効に排除でき、また、安全に消火活動等ができるもの。 |
| |
| (3) 階数が1として算定される建築物等であっても、実質的に複数階となるものは、前項によ |
| るものとする。 |
| |
![]()
![]()