|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
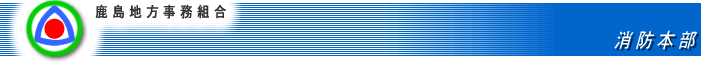 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��P�@���������̋敪 ���������̋敪�͎��̂Ƃ���Ƃ���B �P�@������ �댯��������ړI�łP���Ɏw�萔�ʈȏ�̊댯������舵���ꏊ�������A���z���A�^���N���̑��̍H�앨�y�ѕ����ݔ����тɋ�n�̈�̂������B �Q�@������ �@�@�w�萔�ʈȏ�̊댯���������A���͎�舵�������錚�z���A�^���N�A���̑��̍H�앨�y�ѕ����ݔ����тɋ�n�̈�̂������A���̂Ƃ���敪����B �i�P�j���������� �����̏ꏊ�ɂ����Ċ댯�������A���͎�舵�������� �i�Q�j���O�^���N������ ���O�ɂ���^���N�i�i�S�j����i�U�j�������B�j�ɂ����Ċ댯�������A���͎�舵�������� �i�R�j�����^���N������ �����ɂ���^���N�i�i�S�j����i�U�j�������B�j�ɂ����Ċ댯�������A���͎�舵�������� �i�S�j�n���^���N������ �n�Ֆʉ��ɖ��݂���Ă���^���N�i�i�T�j�������B�j�����Ċ댯�������A���͎�舵�������� �i�T�j�ȈՃ^���N������ �ȈՃ^���N�ɂ����Ċ댯�������A���͎�舵�������� �i�U�j�ړ��^���N������ �ԗ��i�팡�������Ԃɂ����ẮA�O�Ԏ���L���Ȃ����̂ł����āA���Y�팡�������Ԃ̈ꕔ�����������Ԃɍڂ����A���A���Y�팡�������ԋy�т��̐ύڕ��̏d�ʂ̑������������������Ԃɂ���Ă���������\���̂��̂Ɍ���B�j�ɌŒ肳�ꂽ�^���N�ɂ����Ċ댯�������A���͎�舵�������� �i�V�j���O������ ���O�̏ꏊ�ɂ����đ�Q�ނ̊댯���̂��������A�����݂̂��ܗL������̎Ⴕ���͈��ΐ��ő́i���Γ_����x�ȏ���̂Ɍ���B�j���͑�S�ނ̊댯���̂�����P�Ζ��ށi���Γ_����x�ȏ���̂Ɍ���B�j�A�A���R�[���ށA��2�Ζ��ށA��R�Ζ��ށA��4�Ζ��ގႵ���͓��A�����ނ����A���͎�舵�������� �R�@�戵�� �@�@�댯��������ȊO�̖ړI�łP���Ɏw�萔�ʈȏ�̊댯������舵���ꏊ�ŁA���z���A�^���N���̑��̍H�앨�y�ѕ����ݔ����тɋ�n�̈�̂������A���̂Ƃ���敪����B �i�P�j�����戵�� ��狋���ݔ��ɂ���Ď����ԓ��̔R���^���N�ɒ��ڋ������邽�ߊ댯������舵���戵���y�ы����ݔ��ɂ���Ď����ԓ��̔R���^���N�ɒ��ڋ������邽�ߊ댯������舵���ق��A���Ɍf�����Ƃ��s���戵�� �i�Q�j�̔��戵�� �X�܂ɂ����ėe�����̂܂܂Ŕ̔����邽�ߊ댯������舵���戵���ŁA���̂Ƃ���敪����B �E��1��̔��戵���@�w�萔�ʂ̔{���i�@��P�P���̂S��P���ɋK�肷��w�萔�ʂ̔{���������B�ȉ������B�j��15�ȉ��̂��� �E��2��̔��戵���@�w�萔�ʂ̔{�����P�T��40�ȉ��̂��� �i�R�j�ڑ��戵�� �z�Njy�у|���v���тɂ����ɕ�������ݔ��i�댯�����^������D�����痤��ւ̊댯���̈ڑ��ɂ��ẮA�z�Njy�т���ɕ�������ݔ��j�ɂ���Ċ댯���̈ڑ��̎戵�����s���戵���i���Y�댯���̈ڑ������Y�戵���ɌW��{�݁i�z�ǂ������B�j�̕~�n�y�т���ƂƂ��Ɉ�c�̓y�n���`�����鎖�Ə��̗p�ɋ�����y�n���ɂƂǂ܂�\����L������̂������B�j�@ �i�S�j��ʎ戵�� ��L�ȊO�̎戵���ł���A���̂悤�Ȏ{�ݓ��������B �A�@��댯��������{�� �C�@�댯���������{�݁i�{�C���[�{�ݓ��j �E�@�e��[�Ă�{�� �G�@�o�[�X �I�@�������u�A���������u��L����{�� ��Q�@�ݒu�E�ύX���̐\���v�� �P�@�\���P�� �\���́A���ɂ��͈͂��Ƃɐ\�������邱�ƁB �i�P�j������ ���z�����ɐݒu������ɂ����Ă͈�A���O�ɐݒu����ꍇ�ɂ����ẮA��A�̍H�����ƂƂ��A�Q�O���^���N���܂߂���̂Ƃ���B �i�Q�j���������� �P�����ƂƂ���B�������A���p�r�̌��z�����ɐ݂����������ɂ����ẮA�����ƂƂ���B �i�R�j���O�^���N������ �|���v�y�іh������܂ߒ����^���N���ƂƂ���B�������A�����^���N���݂���ꍇ�ɂ����āA�|���v�A�h���瓙�̐\���͈͂͋��L�ݔ����̐\���敪�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B �i�S�j�����^���N������ �^���N��p�����ƂƂ���B�i���ꎺ���ɕ����̃^���N�������Ă������ƂƂ���B�j �i�T�j�n���^���N������ �n�������^���N���ƂƂ���B�������A���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�͂P�̐\���Ƃ��邱�Ƃ��ł���B �A�@�Q�ȏ�̒n�������^���N������̃^���N���ɐݒu����Ă���ꍇ �C�@�Q�ȏ�̒n�������^���N������̊�b��ɐݒu����Ă���ꍇ�@ �E�@�Q�ȏ�̒n�������^���N������̂ӂ��ŕ����Ă���ꍇ �i�U�j�ȈՃ^���N������ �ȈՒ����^���N���ƂƂ���B�������A�Q�ȏ�̊ȈՒ����^���N��ݒu����ꍇ�́A�^���N��p�����ƁA���O�ɂ����ẮA����ꏊ���ƂƂ��邱�Ƃ��ł���B �i�V�j�ړ��^���N������ 1�ԗ����ƂƂ���B�������A�^���N�R���e�i���i�ύڎ��j�ɂ����ẮA�����^���N�R���e�i���܂ߐ\�����邱�ƁB �i�W�j���O������ �P�̉��O���������ƂƂ���B �i�X�j�����戵�� ��p�^���N�A�p���^���N�y�ъȈՃ^���N���܂߂P�̋����戵�����ƂƂ���B �i�P�O�j�̔��戵�� �P�̔̔��戵�����ƂƂ���B �i�P�P�j�ڑ��戵�� �P�̈ڑ��戵�����ƂƂ���B �i�P�Q�j��ʎ戵�� �������̗�ɂ��B�������A�����K���̈�ʎ戵���ɂ����ẮA�P�̎戵�ꏊ���ƂƂ���B ���������̐ݒu�܂��͕ύX�̋��\���敪�͎��ɂ��B �i�P�j�ݒu���\���̑ΏۂɂȂ���� �A�@����������ݒu���悤�Ƃ���Ƃ� �C�@�����������ڐ݂��悤�Ƃ���Ƃ� �E�@���������̋敪��ύX���悤�Ƃ���Ƃ� �i�Q�j�ύX���\���̑ΏۂɂȂ���� �A�@���������̈ʒu�A�\���܂��͐ݔ���ύX�i�y���ȕύX�H���������B�j���悤�Ƃ��@�@�@�@��Ƃ� �C�@���������ɂ����鎟�̋敪��ύX���悤�Ƃ���Ƃ� �E�����戵���ɂ����ĉc�Ɨp���玩�Ɨp�ɕύX����Ƃ� �E�̔��戵���ɂ����đ�P�킩���Q��ɕύX����Ƃ� �E��ʎ戵���̊�K�p�敪��ύX����Ƃ� �E�@�ړ��^���N�������̏�u�ꏊ��ύX����Ƃ��i����~�n���̕ύX�������B�j �G�@�ړ��^���N�������̃^���N�����ւ���Ƃ��@�@�@�@�@�@�@�@�@ �I�@�ύڎ��̈ړ��^���N�������ɂ����Đύڂ���^���N��lj�����Ƃ� �J�@�ړ��^���N�������̎ԗ�����������Ƃ� �L�@���O�^���N�������̃^���N�a�y�э������K�͈ȉ��Ŏ��ւ���Ƃ� ��R�@�ݒu�E�ύX���\���ɕK�v�ȏ��� ���������̐ݒu�E�ύX���\���ɕK�v�ȏ��ނ́A���������̋敪�ɉ����T�ˎ��Ɏ����\�̂Ƃ���Ƃ���B �Ȃ��A�ύX���\���ɂ����ẮA�ύX���e�ɌW�鍀�ڂ̏��ނ�Y�t���邱�ƁB �@
���l �P�@����́A�Y�t��v������́B �Q�@���P�́A���艮�O�^���N�������A�����艮�O�^���N�������ɂ����ẮA��T�͂ɂ�邱�ƁB �R�@���Q�́A�����X�N�R���Q�U���t���h���R�R���u�ړ��^���N�������̋K�������ɌW��葱���y�ѐݒu���\�����̓Y�t���ޓ��Ɋւ���^�p�w�j�ɂ��āv�ɂ�邱�ƁB �S�@���R�́A��ȗߕʕ\�P�̂Q�ɂ��B ���������̋��\�����ނ̕҂���͎��ɂ��B �i�P�j�ݒu���\�� �\-�L�ڂ̕Ғԏ��ɕ҂��邱�ƁB �i�Q�j�ύX���\�� ���������̐\�����ނɂ����ĕύX���e�ɌW����́i�ړ��^���N�������̓]���ɔ�����u�ꏊ�̕ύX�\���̏ꍇ�͐ݒu���\���Ɠ��l�j��\-�L�ڂ̕Ғԏ��ɕ҂��邱�ƁB �������A�ύX���e����������A���ꂼ�ꂪ�Ɨ������H���ł���ꍇ�́A�H�����ڂ��ƂɂƂ�܂Ƃ߂ĕ҂��Ă������x���Ȃ����̂Ƃ���B ��S�@���\�����ނ̋L�ڗv�� ���\�����ނ̋L�ڗv�̂́A���ɂ��B �i�P�j�\�����l���́A�ڑ��戵���ȊO�̐��������̐ݒu���\���̏ꍇ�͊댯���������������戵���ݒu���\�����A�ύX���\���̏ꍇ�͊댯���������������戵���ύX���\�����A�ύX���\���Ɖ��g�p���F�\���Ɠ����ɍs�Ȃ��ꍇ�͊댯���������������戵���ύX���y�щ��g�p���F�\�����A�ڑ��戵���ɂ����Ă͐ݒu���\���̏ꍇ�͈ڑ��戵���ݒu���\�����A�ύX���\���̏ꍇ�͈ڑ��戵���ύX���\�����A�ύX���\���Ɖ��g�p���F�\���Ɠ����ɍs�Ȃ��ꍇ�͈ڑ��戵���ύX���y�щ��g�p���F�\�����Ƃ��邱�ƁB �i�Q�j�L�ڗv�̂́A�L���v�̂ɂ�邱�ƁB �Q�@�\���ݔ����� �i�P�j���������̋敪�ɉ����A��ȗ߂Œ�߂�ꂽ�\���ݔ������̗l���Ƃ��邱�ƁB �i�Q�j���������͈�ʎ戵���ɂ����ẮA�i�P�j�̂ق��A�Q�O���^���N��L����ꍇ�́A ���O�^���N�ɂ����Ă͉��O�^���N�������\���ݔ��������A�����^���N�ɂ����Ă͉����^���N�������\���ݔ��������A�n���^���N�ɂ����Ă͒n���^���N�������\���ݔ�������Y�t���邱�ƁB �i�R�j�����戵���ɂ����ẮA�i�P�j�̂ق��A��p�^���N�A�p���^���N����L����ꍇ�͒n���^���N�������\���ݔ��������A�ȈՃ^���N��L����ꍇ�͊ȈՃ^���N�������\���ݔ�������Y�t���邱�ƁB �i�S�j�e�l���̋L�ڗv�̂́A�L���v�̂ɂ�邱�ƁB �R�@���������O�����Ϗ̎ʂ�,����^���N�������ʏ� �i�P�j���̍s�����ւQ�O���^���N���͉��O�����^���N���̊��������O�����\��������ꍇ�́A���Y�����Ϗi���j�̎ʂ������������O�܂łɐ\�����ɓY�t���邱�ƁB �i�Q�j�^���N�e�ʂ��w�萔�ʖ����̂Q�O���^���N�ɂ����Ď��厎���Ƃ����ꍇ�́A����^���N�������ʏ������������O�܂łɐ\�����ɓY�t���邱�ƁB �i�R�j�됭�ߑ�W���̂Q��S���̋K��ɂ��A�@�ȊO�̌������ɂ���č��i�������̂ɂ��ẮA���̌����ɍ��i�������Ƃ����鏑�ʂ̎ʂ������������O�܂łɐ\�����ɓY�t���邱�ƁB �S�@�ϔC�� �i�P�j�ݒu�҈ȊO�̎҂��\������ꍇ�ɓY�t���邱�ƁB' �i�Q�j�ϔC��̗l���͔C�ӂł��邪�A�ϔC�ҁA��ϔC�ҁA�ϔC���e���ɂ��ẮA�l���W�̈ϔC��i�P�j�i�Q�j�̂悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB �i�R�j���㗝�l�̏ꍇ���A�i�P�j�A�i�Q�j�Ɠ��l�Ƃ���B �i�S�j�ϔC��͋��\�����i���j�ɓY�t�����\�����i���j�ɂ͂��̎ʂ��ł悢���̂Ƃ���B �i�T�j�e���Ə��ɂ����āA���炩���߈ϔC��o����Ă���ꍇ�́A���̓��e�ɕύX���Ȃ��ꍇ�Ɍ���A���\�����ɒ�o�ς̈ϔC��̎ʂ���Y�t����悢���̂Ƃ���B �T�@�댯���K���̈ꕔ�ɘa�肢 �i�P�j�됭�ߑ�23���̋K��ɂ��댯���K���̈ꕔ�ɘa��K�v�Ƃ���ꍇ�ɒ�o���邱�ƁB �i�Q�j�K�v�ȏ��ނ͊댯���K���̈ꕔ�ɘa�肢�A����\�����e�A����\�����R�y�ё�֑[�u���������}�����ł��邱�ƁB �i�R�j�댯���K���̈ꕔ�ɘa�肢�̗l���́A�l���W�̊댯���K���̈ꕔ�ɘa�肢�Ƃ��邱�ƁB �U�@�ύX���\���ɌW���ύX���e�ڍ� �ύX���\���ɂ����ĕύX���ڂ������A�ύX���\�����l���̕ύX�̓��e�����ɏ�������Ȃ��ꍇ�ɓY�t������̂ŁA�ύX���ڂ��ƂɕύX���e�y�ъW���ޓ���������悤�A�l���W�̕ύX���\���ɌW��ύX���e�ڍ��ɋL�ڂ��邱�ƁB �V�@�H���v�揑�y���H���H���\ ���艮�O�^���N�������y�шڑ��戵�����A�H�����Ԃ������ƂȂ�H����c������K�v������ꍇ�ɓY�t���邱�ƁB �W�@�댯������W���� �i�P�j���\���ɌW��댯���ɂ��āA�댯���̎����y�ѐ���Ɋւ���ȗ߁i�������N�����ȗߑ�P���j�Ɋ�Â��A�ށA�i���A�������f�ł��鎑���Ƃ��āA���̂����ꂩ��Y�t���邱�ƁB �A�@�댯�����f�[�^�x�[�X�o�^�m�F���̎ʂ��y�ђ����A�戵�ɂ�����댯���̕����\�i�l���W�̒����A�戵�ɂ�����댯���̕����\�j �C�@�댯���m�F�������ʕ��i�ʂ��j �E�@���S�f�[�^�V�[�g�iSafety Data Sheet ����SDS�j �i�Q�j���\���ɌW��댯�����A�K�\�����A�����A�y���A�d�����̏ꍇ�A���͊��ɓ����h�{���Ŕ���ςł���i�����n�������g���@�댯���f�[�^�W�����ŎQ���j�ꍇ�͏ȗ��ł���B �X�@�댯���������͎戵�������{���v�Z�� �i�P�j�댯���������͎戵���̐��ʋy�є{���̎Z����@��������悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB�������A�ύX���\���ɂ����āA�i���A���ʁA�{���ɕύX���Ȃ��ꍇ�͏ȗ��ł���B �i�Q�j�e���������̎Z��́A�����Ƃ��Ď��ɂ�邱�ƁB �A�@�������E��ʎ戵�� �i�A�j�P���ɂ�����ő�̎戵���ʂ������Ĕ{�����Z�肷�邪�A���̎Z��͓��Y�����������łP���ɂ����Ď�舵���S�Ă̊댯���ɂ��āA���ɂ��敪���{�����Z�肷��B �@�@��A�̍H���Ŏ�舵���댯���i���ʂ̊댯�����z���Ďg�p������̂������B�j�������֓������́i�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j �A�@�@�ȊO�̊댯���Ő����������ŕۗL������́A���͏z���Ďg�p������́i�ȉ��u�ۗL�v�Ƃ����B�j�i��F�����A�M�}�����j �B�@�@�A�A�ȊO�̊댯���Ő����������ŏ������́i�ȉ��u����v�Ƃ����B�j�i��F�{�C���A�o�[�i�[���j �C�@�@�̈�A�̍H���ɂ����Ď�舵���댯���œ����Ă���o��܂ł̊Ԃœ��Y���������ɒ������́i�ȉ��u��v�Ƃ����B�j �i�C�j���Y���������̔{���́A�����A���i�A��̓��ōő�̔{���ɕۗL�y�я���̔{�����������{���ƂȂ�B �i�E�j���X�Ŏ�舵���댯�����قȂ�ꍇ�́A�قȂ���X���ƂɁi�A�j�A�i�C�j�Ɋ�Â��{�����Z�o���ő�ƂȂ���������ē��Y���������̔{���Ƃ���B �i�G�j�i�A�j�̊댯���̋敪�̕ʂɂ��A�P���ɂ�����戵���ʂ́A���ɂ�邱�ƁB �@�@�����E���i�͎��ɂ��B ���@�P���ɓ���H�����J��Ԃ��ꍇ�́A�P�H���Ŏ�舵���댯���̐��ʂɌJ��Ԃ����悶�����ʂƂ���B ���@�P���ɕ����H�����s���ꍇ�́A�e�H�����ƂɎ�舵���댯�����ʂ̍��v�Ƃ���B ���@�P�H���������ɂ킽��ꍇ�́A���ꂼ��̓��ɂ�����戵�����P�H���Ƃ݂Ȃ��ő�ƂȂ�{���̓��̍H���̎戵���ʂƂ���B �A�@�ۗL�͎��ɂ��B ���@���Y�����������̃^���N�ɂ����e���ꂽ�댯�����z���Ďg�p������̂́A���Y�^���N�̗e�ʂ������Ď戵���ʂƂ���B�������A�^���N���܂ߑ��u���Ƀ^���N�̗e�ʈȏ��ۗL����ꍇ�́A�ۗL����ʂ������Ď戵���ʂƂ���B ���@�M�}�����œ��Y���������ȊO�̑��u����댯�����z�g�p����ꍇ�́A���Y�����������̐ݔ��ŕۗL����ʂ������Ď戵���ʂƂ���B �B�@����͎��ɂ��B �{�C���[�A�o�[�i�[�A���̑�����ɗނ��鑕�u�Ŋ댯�����������̂́A�P���ɂ�����ő����ʁi�P�ʎ��Ԃ̍ő����ʂɂP���̉ғ����Ԃ��悶�����ʁj�������Ď戵���ʂƂ���B �C�@�����������E���O�������E�̔��戵�� ���Y���������̖ʐϋy�ђ������@���画�f���āA���ۂɒ�������ő�̗ʂ������Ĕ{�����Z�肷��B �E�@�e�^���N������ �됭�ߑ�T���ɂ��Z�o�����^���N�̗e�ʂ������Ĕ{�����Z�肷��B �G�@�����戵�� �i�A�j�@��p�^���N�A�p���^���N���y�ъȈՃ^���N�ɂ��Ċ됭�ߑ�T���ɂ��Z�o�����^���N�̗e�ʂ������Ĕ{�����Z�肷��B �i�C�j�@�i�A�j�ȊO�̊댯���ɂ��ẮA�{���Ɋ܂߂Ȃ����A���̗ʂ͎w�萔�ʖ����łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���ꂪ������悤�Ɍv�Z����Y�t���邱�ƁB �I�@�ڑ��戵�� �P���ɂ�����ő�ڑ��ʂ������Ĕ{�����Z�肷��B 10�@�댯���戵�����{���W�v�\ ���������͈�ʎ戵���ɂ����āA���X��舵���댯�����قȂ�ꍇ���{���̎Z��Ɋ܂܂�Ȃ��댯��������ꍇ�ɂ́A�l���W�̊댯���戵���ʔ{���W�v�\�ɂ��L�ڂ��邱�ƁB�������A�ύX���\���ɂ����āA�L�ړ��e�ɕύX���Ȃ��ꍇ�͏ȗ��ł���B 11�@���Ə��ē��} ���Ə��ē��}�́A���������̐\���n�i���Ə��j���A�s�̂ǂ̈ʒu�ɂ��邩������悤�ɂ�����̂ł����āA�t�߂̎�ȖڕW���i�����A�S���A�w�Z�A���A�o�X�ⓙ�j�L���A���A�������ň͂�Ŗ��L���邱�ƁB�������A�H�Ɛ�p�n����̎��Ə��ŕύX���\���̏ꍇ�́A�����Ƃ��ďȗ����邱�Ƃ��ł���B 12�@���Ə��S�̔z�u�} �\���ɌW�鐻���������\���n�̂ǂ��̏ꏊ�ɂ��邩������悤�ɂ�����̂ŁA���͂̎{�݂̖��́A�p�r�����ȒP�ɕ��L���A���̒��Ő\���ɂ����鐻���������ǂ̈ʒu�ɂ��邩������悤�ɂ��A�\������F�ʖ��͎������ň͂ޓ����m�ɕ\�����邱�ƁB�������A�e�Ղɐ\���ʒu����������̂ɂ����ẮA�ύX���\���̏ꍇ�A�����Ƃ��ďȗ����邱�Ƃ��ł���B 13�@���������z�u�} ���Y�����������\�����錚�z���A���̑��̍H�앨�A�ݔ��A�@�퓙�̔z�u�������ق��A���͂̐��������A�����K�X�{�y�э\�z���A�H�앨���̑��݊W����悤�ɂ�����̂ŁA���ɂ�邱�ƁB �A�@�ۈ������A�ۗL��n�A�~�n�������̕����L�ڂ������̂ł���B�������C�ۈ������ɂ��ẮA�z�u�}�ɂ��ꂼ��̕ۈ��Ώە�������̋������K��l�ȏ�ł��邱�Ƃ����m�ȏꍇ�A���̎|���L�ڂ��邱�Ƃɂ�苗����}�����Ȃ����Ƃ��ł���B �C�@�������������̓��A���A�@��ɂ́A���́A�L���A�ԍ��i�@�탊�X�g�ƍ��v������́B�j��t���A���댯���ɌW����̂ɂ��Ă͂��̎|��������B �E�@�������������ӂ̌��z���E�H�앨�E�����K�X�{�ݓ��̕ۈ��������ɂ��āA�^���N���A���a�y�у|���v�A��b�����瑊�݂̋�����������悤�ɂ���B �G�@���O�^���N�������A�����^���N���������אڂ���^���N�Ԃ̋����y�у^���N�Ɩh����̋����L����B �I�@�ۗL��n�́A�\�����Ɋ܂߂���̂Ƃ���B 14�@�H���T�v������ �H���T�v�������́A�H���T�v�}�i�t���[�V�[�g�j�ƕ����Ċ댯���̐����y�ю戵���̊T�v��c���ł���悤�ɂ��邽�߂̂��̂ŁA�P�Ȃ�v���Z�X�̐����ł͂Ȃ��B���ɁA��q�̍H���T�v�}�A�@�탊�X�g��O�q�̐\�����̑S�̔z�u�}�Ƃ̊֘A�ɒ��ӂ��Ď��ɂ�邱�ƁB �A�@������������ŏI�H���܂ł̕������x�i���e���̕i�����ʁj�Ƃ��A�L�ڍ���ȂƂ��́A�H���T�v�}���ɋL�����Ă��悢�B �C�@�^�]���ɂ�����e���A�����ɂ�������M�A�����������̍H���̂�����̂́A�������x�A�������́A�����M�����L�ڂ���B �E�@�댯������舵���ɂ������ė\�z�����댯���Ƃ��̏����y�ђʏ펞�̗\�h�[�u���L�ڂ���B �H�@�H����ʼn��x�∳�͂̏㏸�A���ʂ̋}���ȕω��A��d�A��p���̕s�����ُ��Ԃ����������Ƃ��A�ǂ̂悤�Ȗh�~�[�u���ł���悤�ɂȂ��Ă��邩�ɂ��ċL�ڂ���B �I�@�ύX���\���ɂ����ẮA�H���̕ύX���e�ɂ��ċL�ڂ���B 15�@�H���T�v�}�i�t���[�V�[�g�j �i�P�j�H���T�v�}�́A�H���T�v�������̓��e����₷���}���������̂ŁA�H���T�v�������ƕ����ēǂ݂Ƃ����̂ł��邱�ƁB �i�Q�j�댯���A��댯�����̍H���̗�����L�ڂ��邱�ƁB �i�R�j�H�����̋@��A���́A�ԍ����́A�@��S�̔z�u�}�y�ы@�탊�X�g�Ɠ���̂��̂Ƃ��A��v�Ȍv��y�ш��S���u�̎�ނƎ��t���ʒu�����L���邱�ƁB �i�S�j�H�����ɂ����铃�A�����̈��́A���x���L�ڂ��邱�ƁB �i�T�j�H�����ɂ�����댯�����C���y�тQ�O���^���N�ɂ��āC�������邱�ƁB �i�U�j�H�����ɂ�����댯���̎戵���ʂ́A���A���A���͂P�o�b�`�^���ԂƂ����悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB �i�V�j���u����o�镛����(�댯��)�̑ԗl�y�ѕi���A���ʕ��тɏ������@���L�ڂ��邱�ƁB �i�W�j�����ȒP�Ȑ��������������A�댯���̐����A�戵���̖ړI�ō����A�����̏����ł̍����댯�A���x�E���J�ُ̈�㏸�A���ʂُ̈�ω��A�^�]��ُ̈펞���ɋN�����锚�����\�������̊댯��h�~���邽�߂̊e����S���u��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ��Ă��H���T�v�}�ɋL�����邱�ƁB 16�@�@�탊�X�g �i�P�j���������\�������̑S�@��̊T�v��c���ł�����̂ł��邱�ƁB�������A�ύX���\���ɂ����ċL�ړ��e�ɕύX���Ȃ��ꍇ�͏ȗ��ł���B �i�Q�j�l���͗l���W�̋@�탊�X�g�ɂ��B 17�@�������������ݔ��A�@�퓙�z�u�} �i�P�j���������\�������̐ݔ��A�@�퓙�ɂ��Ĕz�u�������邱�ƁB �i�Q�j�@��ɂ����ẮA�@�탊�X�g�Əƍ��ł���悤�L�ڂ��邱�ƁB 18�@���ϐ} �����戵���ɂ��āA�����戵���̕~�n�̋��ϐ}��Y�t���A���̋��ϐ}�ɉ��O���͉��������戵���̕ʂ����f�ł����n����L�ڂ��邱�ƁB 19�@���z���C�H�앨���\���} �i�P�j���������ɑ����錚�z���A���͍H�앨���̍\������������̂ŁA���ʐ}�i���z�������̐ݔ����̔z�u�����������́B�j���ʐ}�i�l�ʁj�y�ђf�ʐ}�i��\�I�Ȓf�ʁj�ł���B�������A��K�͌��z�����͍H�앨�̈ꕔ�ɐ݂�����F�A���͖������u�ɌW�錚�z���A�H�앨�̑S�̐}�́A���̊T�v�}�ō����x���Ȃ��B �i�Q�j��v�\�����i�ǁA���A���A�͂�A�������j�ɂ��ẮA���ʐ}���ɍ\�������L�ڂ��邱�ƁB��v�\������ω\���Ƃ��A���͕s�R�ޗ��ő���ꍇ�ō��y��ʑ�b�̔F��i���g�p����Ƃ��́A����{�H�ɂ����̂������A�F��ԍ����L�ڂ���A�ʓr�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B �i�R�j���y�яo�����ɂ��ẮA���ʐ}���Ɉʒu�A���@�A�\�������L�ڂ��邱�ƁB�����͏o�����̖h�ΐݔ����ō��y��ʑ�b�̔F��i���g�p����ꍇ�́A�F��ԍ����L�ڂ���A�ʓr�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B �i�S�j�����戵���ɂ����ẮA��L�ȊO�ɃA�C�����h�A�h�Ε��A�������������̍\���}����Y�t���邱�ƁB 20�@���ʋy���r���W�} �i�P�j���������̑���������̊댯�����R�ꂽ�ꍇ�̔�U�h�~�ݔ��y�щJ�����̏�������ݔ����ł����āA���ʁA�r���a�A�����ݔ����܂߁A����炪��������̂ł��邱�ƁB �i�Q�j�u�n�Ֆʁv�́A�R���N���[�g���t�̂��Z�����Ȃ��ޗ��ŕ����A����������݂��A�\���A���@�A�X��������悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB �i�R�j�u�͂��v�́A���̋�悩��댯�������o����̂�h�~���邽�߂̂��̂ł��邩��i�n�Ֆʂɐ݂���ꍇ�́A�R���N���[�g���Ƃ���̂��悢�B�j�\���A���@�A�r���ٓ���������悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB �i�S�j�u���������v�́A��U�h�~�ݔ��O�ɘR�k�����댯���i���ɗn���Ȃ����̂Ɍ���B�j���A�J�����ɂ��r���a�ɗ��ꍞ�܂Ȃ��悤�ɂ�����̂ł��邩��A�\���A���@�A�r���@�\����������悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB �i�T�j�r���a�A�����ݔ��ɂ��āA���ʐ}���Ɉʒu�y�ѐ��@���L�ڂ����ꍇ�́A�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B 21�@�댯���ɌW�铃�A���A�|���v���@�����b�} ���������\�������̊댯���ɌW�铃�A���A�|���v���@��̊�b�}�ł����āA���@�A�z�ؓ��������镽�ʐ}�A�f�ʐ}�ł��邱�ƁB 22�@�댯���ɌW���^���N�\���} �댯���ɌW��^���N�Ƃ́A�댯�������͎�舵���^���N�������A���̍\���}�Ƃ́A���Y�^���N���@�߂ɓK�������Z�p�I�ɓK���Ȃ��̂ł��邩������悤�ɂ�����̂ł���A����}�ɍ\���y�юd�l�i�^���N���@�A���A�ގ��A�m�Y���̈ʒu�y�ь��a���j�A�p�r���тɎg�p�����A�v���������L�ڂ������̂ł��邱�ƁB 23�@�댯���ɌW���@��\���} �댯���ɌW��@��Ƃ́A�^���N�ȊO�̊댯�������͎戵��������@��������A���̍\���}�Ƃ́A���@�A�ގ��A������������\���}���̓J�^���O���Ŏd�l����������̂ł��邱�ƁB �Ȃ��A���K�͂Ȋ댯���戵�ݔ����ɂ��ẮA�z�u�}���Ɉʒu�A�ގ������L�ڂ����ꍇ�́A�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B 24�@�댯���ɌW��@��������ݔ��\���} �i�P�j��U�h�~�ݔ��A���x���葕�u�A���͌v�A���S���u�A�Ђ�h�~���邽�߂̕����ݔ����̍\������������̂ł��邱�ƁB �Ȃ��A�z�u�}���Ɉʒu�A�@�\�����L�ڂ����ꍇ�́i��^�����v�����g���A�����̐ݔ���ݒu����{�݂ɂ����ẮA�t���[�}���ɕ����ݔ��̊T�v���L�ڂ��邱�Ƃ��ł���B�j�A�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B �i�Q�j�^���N�ɂ����ẮA�ʋC�ǁA�t�ʌv���̐}�ʂ�Y�t���邱�ƁB �Ȃ��A�@��\���}���Ɏ�t�ʒu�A�ގ������L�ڂ����ꍇ�́A�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B �i�R�j�F��i�ȊO�̉Ƃ��njp��ɂ����ẮA�\���}�y�ы��x�v�Z���i���a�T�U�N�R���X���t���h���Q�O���y�я��a�T�V�N�T���Q�W���t���h���T�X���ɂ��B�j��Y�t���邱�ƁB 25�@�댯���ɌW���^���N�e�ʌv�Z���y�э\���v�Z�� �i�P�j�e�ʌv�Z���́A�됭�ߑ�T���A��ȗߑ�Q���A����R���ɂ��v�Z�������̂ł��邱�ƁB �i�Q�j�\���v�Z���́A���O�^���N�ɂ����Ă͒n�k�A�����ɑ������v�Z�Ƃ��Ċ�ȗߋy�ъ덐���̋K��ɂ��v�Z�������́A���J�^���N�ɂ����Ă͑ψ����̋��x�v�Z���������́A�n���^���N�ɂ����ẮA�n�ϗ͋y�ѕ��͓��̌v�Z���������̂ł��邱�ƁB 26�@�댯���ɌW���@��\���v�Z�� ���̌v�Z���́A�^���N�ȊO�̓��A���ނɂ����Ēn�k�A�����ɑ��Ĉ��肵�Ă��邩�ǂ����A���J���ɑς����邩�ǂ����f������̂ł���A25�i�Q�j���͓��{�Y�ƋK�i���ɂ��v�Z�������̂ł��邱�ƁB�������A�ގ��̋@��ɂ����ẮA��\�I�ȋ@���I�����ēY�t����悢���̂Ƃ���B 27�@�h����\���} ���̍\���}�́A�z�E���@�A�z�NJђʕ��ی�[�u�A�r���فA�~���A�K�i���������镽�ʐ}�A�f�ʐ}�ł��邱�ƁB 28�@�h����e�ʌv�Z���y�ы��x�v�Z�� �i�P�j�h����̗e�ʌv�Z���́A�덐����S���̂Q�̌v�Z���Ōv�Z�������̂ł��邱�ƁB �Ȃ��A�Q�O���h����ɂ��Ă����l�Ƃ���B �i�Q�j���̋��x�v�Z���́A���O�����^���N���j�ɂ��댯�������o�����ꍇ����ɑς����邩���f������̂ł��邩��A���a�T�Q�N�P�P���P�S���t���h���P�U�Q���u�h����̍\�����Ɋւ���^�p��ɂ��āv�ɂ��v�Z�������̂ł��邱�ƁB 29�@�댯���ɌW���z�ǐ}�y�єz�ǎx�����\���} �i�P�j�z�ǐ}�́A�����Ƃ��Ċ댯���ɌW��z�ǂɂ��ċL�ڂ�����̂Ƃ��A���ʐ}�ɉˋ�A�n��A�n�����[�g�̕ʋy�эގ��A�nja�A���́A�ً}�Ւf�فA���S�فA���̑���������悤�ɂ���ƂƂ��ɁA�z�ǂ�핢����ꍇ�͂��̍ގ��A�M�����ɂ��Ė��L���邱�ƁB �i�Q�j�z�ǎx�����\���}�́A�x�����̊T�v����������̂Ŕz�ǂ̌Œ���@�A�ωΐ��\�ɂ��ċL�ڂ���ƂƂ��ɁA�x�����̌`�e�킠��ꍇ�͑�\�I�Ȃ��̂ō����x���Ȃ��B 30�@�댯���ɌW���z�ǎx�������x�v�Z�� �i�P�j���̌v�Z���́A�댯���z�ǎx�������n�k�y�ѕ����ɑ����S�ȍ\���ł��邩�ǂ������f�ł�����̂ł��邱�ƁB �i�Q�j��^�̎x�����ɂ����ẮA�v�Z�̂��߂̏������y�ьv�Z���ʂ݂̂��L�ڂ������̂Ƃ��邱�Ƃ��ł���B 31�@���C�ݔ��y�щR�����C���r�o�ݔ��\���} ���z�����ɂ����āA�댯���̎戵��������ꍇ���C�ݔ������K�v�ƂȂ邪�A�����̐ݒu�ꏊ�y�э\������������̂ł��邱�ƁB 32�@�d�C�ݔ��y�ѓd�C�z���} �i�P�j�댯�ꏊ�i�R�����C���R�ꖔ�͑ؗ��A���炩�̓_�Ό��ɂ�蔚�����̂�����̂���ꏊ�������B�ȉ������B�j���̓d�C�ݔ��i�z�d�ՁA���d�ՁA�ψ���A�d���@�A�Ւf�@�A�R���Z���g�A�Ɩ����j�̐ݒu�ꏊ��������悤�ɂ���ƂƂ��ɁA�d�C�z���̃��[�g�y�э\���i�{�H���@���j���L�ڂ������̂ł��邱�ƁB �i�Q�j�댯�ꏊ�ȊO�̓d�C�ݔ��ɂ��Ă͏ȗ����邱�Ƃ��ł���B�܂��A�댯�ꏊ�ȊO�̓d�C�z���ɂ��ẮA��d�������瓖�Y���������̊댯�ꏊ�Ɏ���z���̃��[�g�̂L�ڂ���悢���̂Ƃ���B 33�@�d�C�ݔ��\���} �i�P�j�댯�ꏊ���ɐݒu����d�C�ݔ��ɂ��Ă��̍\������������̂ł��邱�ƁB �i�Q�j�\���}�ȊO�ɖh�����\�ɂ��Ďd�l���킩��J�^���O���ł悢���̂Ƃ���B �i�R�j�z�u�}���Ɉʒu�A�@�탊�X�g�ɖh���\���L�������L�ڂ��邱�Ƃɂ��ʓr�\���}�̓Y�t��v���Ȃ��B 34�@�𗋐ݔ��T�v�} �𗋐ݔ��̐ݒu�ꏊ�A�\���A�ی�p������������̂ł��邱�ƁB �Ód�C�����ݔ��̐ݒu�ꏊ�A�\��������������̂ł��邱�ƁB 36�@���h�p�ݔ����z�u�} ���h�p�ݔ����ɂ��āA�\���A�v�Z�����ڍׂ͏��h�p�ݔ������H�͏o�ɂ�菈��������̂Ƃ��A���\���ɂ����ẮA�z�u�y�т��̊T�v��������悤�ɋL�ڂ��邱�ƁB 37�@�����e��敪�} �e��Ŋ댯��������ꍇ�́A�e��̌`��A���A���������A�W�ϋ敪������������̂ł��邱�ƁB 38�@�����ݔ��}�y�т��̑��̐ݔ��} �i�P�j�����戵���Ŏg�p�����ԋ@�APOS���ɂ��āA�J�^���O���Ŏd�l�̕�������̂ł��邱�ƁB �i�Q�j�댯������舵���E�H�[���^���N���ɂ����ẮA���̍\������������̂ł��邱�ƁB 39�@�ً}���������� ���������ɂ�����ً}���̑ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�����������̂ł��邱�Ƃ���A���̎����ɗ��ӂ��Ă��̊T�v���L�ڂ��邱�ƁB �A�@�����������C���ً̋}��~�[�u �C�@�ُ펞�����㏸�h�~�[�u �E�@������~�ܓ��̓����[�u �H�@��]��������̘R�k���̑[�u �I�@���o�����m���u�̊T�v �J�@����V�X�e���̊T�v�i�ꕔ��~���͑S�ʒ�~�j �L�@���̑����h������x��ƂȂ�ݔ��̊T�v�i���ː����ʌ��f���j 40�@�댯���̎戵���ɔ����댯�v���ɑΉ����Đݒu����ݔ����Ɋւ��鏑�ޓ� �@�@�@�됭�ߑ�7���̂R�ɒ�߂鐻�����y�ш�ʎ戵���ɂ��āA�ݒu���̏ꍇ�́u�댯���̎戵���ɔ����댯�v���ɑΉ����Đݒu����ݔ����Ɋւ��鏑�ށv���A�ύX���̏ꍇ�́u�댯���̎戵���ɔ����댯�v���ɑΉ����Đݒu����ݔ����ɂ��ĕύX������̂ɂ����ẮA���Y�ݔ����Ɋւ��鏑�ށv��Y�t���邱�ƁB 4�P�@���̑��K�v�Ƃ���}�� �i�P�j�댯���戵�ݔ��Ɗ֘A�̂����Ώېݔ��� �댯���戵�ݔ��Ɗ֘A�̂���i�댯���̒������͎戵������S���ɉe��������̂������B�j��Ώېݔ��y�ъ댯�ꏊ�ɂ���댯���戵�ݔ��Ɗ֘A�̂Ȃ���Ώېݔ��́A�z�u�}���ɖ��́A�h���\��(�h������܂ށB)�����L�ڂ��邱�Ƃɂ��A�ʓr�\���}���ȗ����邱�Ƃ��ł���B �i�Q�j�댯���戵�ݔ��Ɗ֘A�̂Ȃ���Ώېݔ� �댯���戵�ݔ��Ɗ֘A�̂Ȃ��i�댯���̒������͎戵������S���ɉe�����Ȃ����̂������B�j��Ώېݔ��Ŋ댯�ꏊ�ɂȂ����̂́A�z�u�}���ɖ��̂��L�ڂ��邱�Ƃɂ��A�ʓr�\���}�����ȗ����邱�Ƃ��ł���B �i�R�j���̑��K�v�Ƃ���}����Y�t���邱�ƁB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
�{�T�C�g�̑S�Ă̌����͎����n�������g���ɋA��������̂ł���A���f�]�ڂ��邱�Ƃ��֎~���܂��B